昨年末、もはや僕自身も忘れていた、スロバキアのタトラ(Tatry)山地を冬に歩いてきた時の記録。 こちらの後編では実際に山を歩いた2日間の行程と写真を掲載。
初スロバキア、初ヨーロッパの雪山登山だったが、結果的に猛省する山行になってしまった。慢心って怖いね。自らを登山上級者と勘違いしてしまったライトハイカーの反省の記録として読んでいただきたい。
前編: 東欧の冬山へ。スロバキア・タトラ山地を歩く(前編)準備とアプローチ
Day1
1日目は4.5 ~ 5.5時間ほど歩く予定。そう、事前にわかっていたはずなのに、出発した時間が遅すぎた。
1日目のルート(表記は実際にかかった時間)

スタート地点はTatranska Lomnicaというロープウェイ駅。スキー客でごった返していて気が緩む。

しばらくはロープウェイの架線に沿ってトレイルを歩く。
ところどころにマーキングがあって迷う心配はない。

最初の2時間半、Rainerova chataまでの道は冬のリゾート地といった感じで、登山装備のない観光客がほとんど。
お父さんにそりを引かれてやってきた子供。

ご覧のように見通しも良くトレースもついている。

標高1,301mのRainerova chata。宿泊はできないが、本場のグリューワインが飲める(ちなみに中もめっちゃ寒い)。寒い中のホットワインは格別。カジュアルなハイキング層はこの辺りで引き返すことが多いようだ。

さらに30分歩くと、山岳エリアへの入り口になる山小屋、Zamkovskeho chataに到着。標高はすでに1,475m。

このZamkovského chataは、日本の八ヶ岳あたりの山小屋の雰囲気とよく似ていた。ここに一泊してもよかったかな。
Zamkovského chata (Zamka)
+421 905 554 471 / +421 902 266 115

ランチ。お隣の国ハンガリーの民族料理、Goulash(グーラッシュ)を食べる。

と、ここまでは天気も悪くなく視界も開けているし、難所も皆無で、安心しきってしまったのが完全な間違いだった。

陽が暮れ、吹雪の中の直登へ。
そして、ランチを済ませてからから本日のゴール、山小屋Téryho chateまではほぼ写真がない。
歩き始めたのは15時ごろ、空の雲行きも怪しくなってきて気温も下がり、雪山登山の様相を呈してくる。しばらく歩いて16時を過ぎたころ、長い直登があらわれるが、登っている途中で陽が暮れてしまった。完全に自分の時間配分ミスである。冬山に慣れてきた慢心というか驕りというか、時間に余裕を持った計画を怠ってしまった。
山小屋まではもう30分ほどでたどり着く勘定だったが、天候もみるみるシビアになっていき、視界不良でトレースも消え去った。キックステップ(雪の斜面につま先を蹴り入れて滑らないように登る技術)をしないと進めない登りが続く。
ヘッドライトを取り出すが、弱々しく斜めに降る雪を照らすばかりで、Téryho chateまでどれぐらいの距離なのか見当もつかない。
引き返すか、このままいくか。
と、そこで、前方にちらつく二つのライトがあった。同じくTéryho chateを目指す登山者だろう。大声で彼らに呼びかける。「ハロー! もう僕は戻ろうと思う!」 すると、「あと少しで着くはずだから来なよ!」という。
力を振り絞って男性二人組に合流すると、クライミングギアをぶらさげていて、吹雪を照らす光度の強いライトも持っている。どうやら経験値は豊富そうだ。現地の人らしい。非常にカッコ悪いことこの上ないが、山小屋までのルートファインディングはお願いすることにした。
真っ暗闇の中、それから慎重にいくつかの丘を巻き、30分(体感的には1、2時間)ほど進んだころ、ついに山小屋の光が見えた。「うおぉ!」という声が自然に出る。最後の100メートルはまた直登だ。ここぞとばかりに先頭に出て感謝のラッセルを決め込む。
鼻水ダラダラで小屋の入り口にたどり着き、彼らと握手を交わす。名前はもう忘れてしまったが、彼らから「Ryoに連れてきてもらったな」という声をかけてもらった。いやいやあなた方がいなかったら僕こそ危なかった。あとで聞いたところによると彼らはガイドらしい。本職の方だったとは。
山小屋Téryho chateでのひと時
Téryho chateは標高2,015mに位置する、食事も宿泊もできるハット。外は吹雪だが中はストーブも炊かれていて暖かい。
タトラの山小屋の作りは日本とそこまで大差はないと感じたが、料金は格段に安い。
二食(朝・夕)込みのドミトリーで37EUR。
ベッドだけだと23EURというから驚き。

山小屋での晩御飯は、またグーラッシュ。

ビーフシチューと牛スジを合わせたような料理といえば一番近いかもしれない。日本のシチューよりもパプリカ粉など香辛料が効いていて飽きがこない。この日の到着が遅すぎてスタッフと同じ部屋に詰め込まれたが、そんなことはどうでもよく、暖かいベッドでお腹いっぱいで眠りにつく。
Day2
二日目は昨日より行程も短い。途中までは同じ道を降るだけだ。昨日の反省を生かし、早めに出発することにする。

分厚い雲の隙間に時折晴れ間が顔を覗かせる天気の中、歩き始める。

昨日あれだけ苦労したのが嘘のように、わかりやすく一直線に下っていくだけ。
今日は緊張も解けて、他のハイカーと話して写真を撮らせてもらう余裕もあった。途中まで同じ道を下った現地のグループ。







スロバキアの首都ブラチスラヴァでJavaのエンジニアをしているらしい男性とも出会った。
あっという間に今回のハイクの終着地Hreibienok。ロープウェイの駅だが、レストランや体験施設などあってたくさんの人で賑わっていた。


ロープウェイに乗って帰った。

ハイクを終えて
反省した点を中心に今回の所感をまとめておく。
装備はどれだけあれば安心か
寒さは恐れていたほどではなく、前編に載せた衣類で十分すぎるほど。今回はPatagoniaのナノエアが活躍した。山行中ほぼ着通し。何回も山に持って行っているが対応できる温度の幅が本当に広い。
Patagoniaの名作保温着、ナノエアフーディ(nano-air hoody) のレビュー。
地図は出発当日に現地の土産屋で買った。等高線のついた折りたたみマップが7EURで買える。
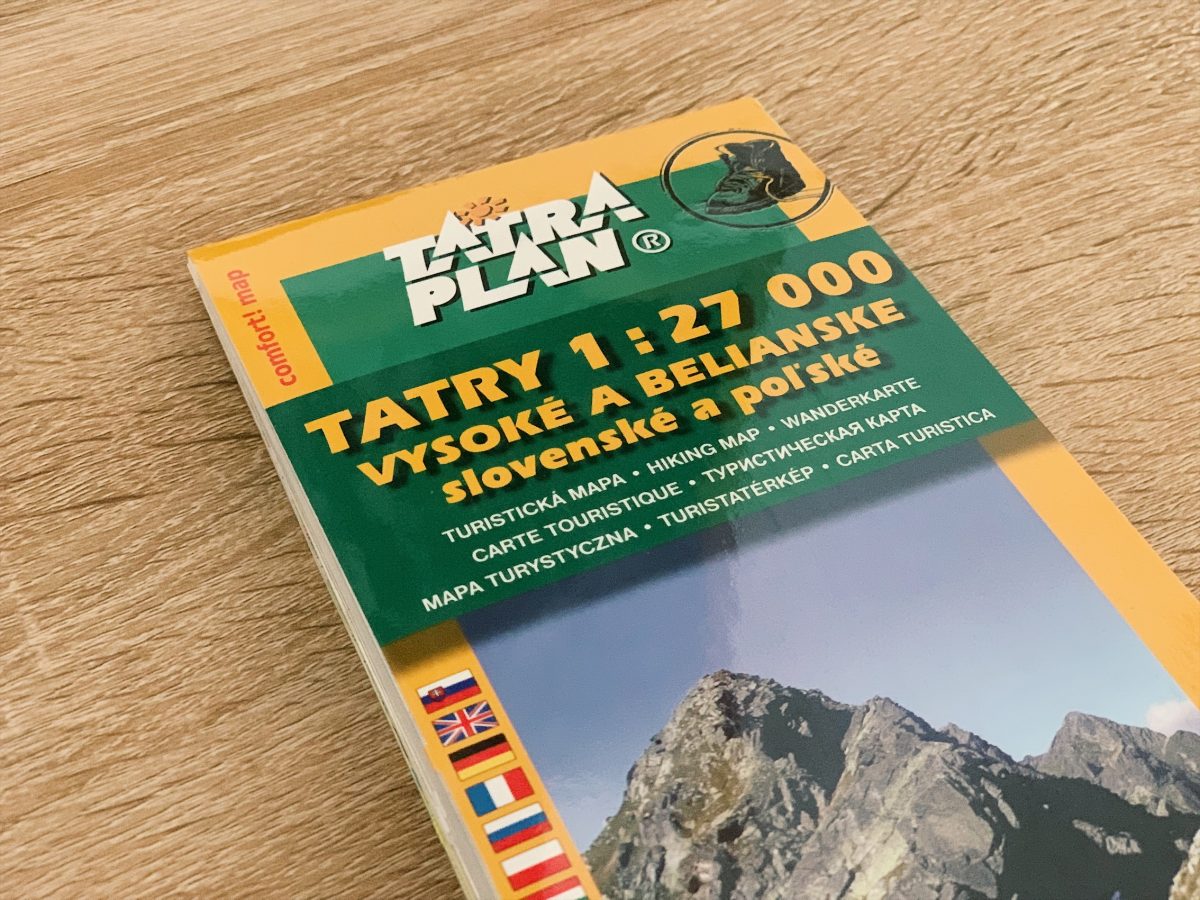
そのほかに持って来ればよかったと思ったものリスト
- 冬山用のGPS
- 海外で単独行する人は絶対に持っておいたほうがいい。吹雪の中でロストしかけた今回それを痛感。
- スペアの手袋
- 一日目、陽が暮れかかった頃に手袋を落とす痛恨のミス。スペアがなかったので二日目は素手での歩きになってしまった。やはり冬山でスペアは必須。
- ピッケルとアイゼン
- 特に一日目の直登。赤岳ほどの強風ではなかったが、完全にピッケルとアイゼンは必要なレベル。迷ったら、よりテクニカルな局面に対応できるギアを持っていくのが望ましい。
- 吹雪の夜も照らせる光度の強いライト
- 自分の持っていたライトでは体感的に目の前しか照らせなかった。冬山装備をウルトラライトな感覚で考えたらダメだという例(当たり前だ)。5 ~ 10mくらい先まで照らせるだけで安心感が違う。
時間の見積もり
今回のピンチを招いた要因は、日暮れの時間を甘く見ていたこと。しかもヨーロッパのコースタイム表記は、日本の地図表記よりも厳しいと感じた。
脚も長く、年配の人でもスイスイ歩いていく人もこっちでは多い。日本でのコースタイムより速く歩けるという自信がある方でも、ヨーロッパではコースタイムの一〜二割増くらいで換算しておくのがいいだろう。
コースの選定について
スロバキアの登山の情報は日本語は皆無、あっても夏山の案内がちょっとくらいしかネットには見当たらなかったので、現地に行くまで自分が想定していたトレイルが存在するのか、若干の不安を抱えていた。
実際に行ってみると、とても柔軟にハイキング・ルートが組めることがわかった。
複数日になるが、スロバキア側から山々を越えて北上し、ポーランドまで歩き通すことも可能だ。北アルプスほど大きな山域でもないし、ロープウェイ駅を含めてエスケープ・ルートも豊富、かつ山小屋ではしっかりと食料も補充できるので、移動日含めて数日から1週間ほどの夏のロングハイクにもぴったりだと思う。
ヨーロッパでは山小屋を繋いで歩くのが基本で、山域内にテントを張ることが禁止されていることも多いが、今回のタトラ山地では、夏であれば一応テントサイトも存在する。
言語の問題
英語が話せれば現地では概ね問題ない。ドイツ語の方が得意というスロバキア人にも何人か出会い、「何でドイツに住んでるのにドイツ語話せないんだ?」と。おっしゃる通りです・・・。
タトラ山地を登る日本人の方へ
登山の事前調査をするにあたり、日本語での情報がほぼ皆無だったのがこの記事を書いた理由。
今回の冬山ルートのレベルとしては、厳冬期の燕岳よりは難易度が高く、赤岳よりは若干イージーといえばイメージできるだろうか。
もちろん天候にもよるので一概にはいえないが、少なくとも日本の厳冬期の2,500m以上の冬山の経験値がないと、トラブル含め判断が難しい場面があると思う。
そして僕にとって重要だったのが「ガイドを雇わなくていい」ということ。冬においても自力で好きなルートを歩ける自由さは捨てがたい。
もちろん英語を話すガイドを雇って地域や歴史の説明をしてもらいながら歩くのも楽しいと思う。今回の下山口Starý Smokovecという麓の街には博物館があり、同じ建物にガイドのオフィスも入っていたようなので、探せば他にもいくつか見つかると思う。
その博物館で学芸員をしているIvanaとの出会いも印象的で、彼女自身も夏はハイカーを案内しているとのこと。興味のある人はご一報いただければ連絡先を紹介します。

夏も冬もタトラは本当に魅力的な山々で、現地の人もフレンドリー。物価も安いし、オーストリアやハンガリーなど周辺国の観光も兼ねてヨーロッパ登山がしたいという方にぜひオススメしたい。
最後に
長いブランク明けの冬山登山ということもあり、反省の多い山登りになった。

ただ、ヨーロッパの冬山を何はともあれ歩き通したことは自信にも繋がった。
冬山では時間を共有したハイカー同士が親しくなる、夏山とは違った良さがある。
日本人と違うのは、トレイルで追いつかれても声をかけない限りは道を空けて抜かせたりしないこと。むしろ話しかけてみて会話を楽しむといいと思う。みんな写真撮影も快くOKしてくれた。
今回訪れた地域はHigh Tatras(ハイタトラス)とも呼ばれるらしく、反対にLow Tatrasはスロバキアのほぼ中央に位置する山域で、近い将来そちらもぜひ訪れてみたい。

